Vol.3 僕は被災者なのかな?(前編)
3.11と言えば東日本大震災があった日です。今思い返しても恐ろしい映像が、連日テレビで放送されていた記憶があるのですが、僕は…というか、僕に限らず多くの人が、おそらく日本中のほとんどの人が“津波の恐ろしさ”を生まれて初めて目にした日だったのではないかなぁ。とりあえず、いつものように便利な百科事典Wikipediaさんによると、「東日本大震災」は次のように定義してあります。
“東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい)は、2011年(平成23年)3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故(放射能汚染)による大規模な地震災害(震災)である。
東日本各地での大きな揺れや、大津波・火災などにより、東北地方を中心に12都道府県で2万2,325名の死者・行方不明者が発生した(震災関連死を含む)。これは明治時代以降の日本の地震被害としては関東大震災、明治三陸地震に次ぐ被害規模である(震災関連死を除いた比較)。
発生した日付から、3.11(さんてんいちいち、さんいちいち)と称されることもある。英称は Great East Japan Earthquake など”
Wikipedia「東日本大震災」より引用
上記引用の以下には、地震の規模や震源地などといった情報が記載してあり、更に続いてそれら地震によってもたらされた一連の災害を指す名称として、「東日本大震災」という名称を時の政府が決定したこと、各地の被害や震災の影響などの細かい情報などなどが得られますが、ここでは「東日本大震災とは何ぞや?」の部分だけ使わせてもらいます。Wikipediaさんいつもありがとう。もう便利過ぎて呼び捨て出来ない、“さん”づけですよ。
ちょっと被害の規模も大きい、というか大き過ぎますし、犠牲者の皆さんやご遺族の皆さん方、被災者の皆さん方を思うと明るい話には変えにくい出来事ですし、ましてや僕自身が震災の当事者でもないので、あまり深い話も出来ませんし暗くなり過ぎないうちに哀悼の意を表して話を切り替えたいと思います。改めて、東日本大震災の犠牲者の皆さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。
で、震災というといつも思うのは、僕は正確には“被災者”の定義を理解出来ていませんで、ちょっと調べてみようかな…というのも、1.17ですかね「阪神・淡路大震災」を僕は京都の亀岡市並河町というところで、初めての一人暮らしをした時期に経験しておりまして、僕自身は被災者になるのかどうかというのが、どこかで災害が起きるたびに思い起こされては気になってですね…ほぉほぉ、なるほどそういう定義でそういう分類があるんですか。Wikipediaさんが常に正しい情報を提示しているのかは定かではありませんが、とりあえずみんな大好きWikipediaさんによると以下の通りでした
“被災者(ひさいしゃ、英: Victim, Disaster victim)とは災害を被った者。地震・台風等の天災や、事故・事件等の人災にあった人(人々)が含まれる。ただし、事件や事故の場合は被害者と呼ばれて、被災者と区別されることが多い。”
“被災者の分類
1970年5月31日のアンカシュ地震の被災者を研究したS・W・ドゥダシクの著書『Victimization in natural disaster. Disasters(災害の中の被災者と災害)』(1980年発行)の中において、被災者は、以下の4つのグループに分類されている。
一次被災者 (Primary victims)
→災害の影響により何らかの損失等を受けた人(または人々)近接被災者 (Context victims)
→災害の影響または結果によって、直接・間接的に影響を受けた人(または人々)周辺被災者 (Peripheral victims)
→被災地域と強い関係を持ち、その結果として影響を受けた人(または人々)進入被災者 (Entry victims)
→被災地に外部から集まってきた人(または人々)たとえば火災の場合、"火災で家を焼かれた人"は一次被災者となり、"火災の影響は受けなかったが、災害後の臭気等に悩まされる隣家"は近接被災者、"その家に縁を持つ近親者"は周辺被災者となる。また、"消火活動をする人"は進入被災者になりうるのである。
これに対して、ニュージーランドの精神科医A・J・W・タイラーとA・G・フレイザーは、もっと細かい分類をしている。2人の場合、近接被災者から進入被災者を二次被災者から四次被災者としていて、四次被災者以降に五次被災者と六次被災者を設けている。五次被災者は、災害に関与していなくても精神的に苦痛を感じる人(または人々)。六次被災者は、直接的な被災を免れたが間接・代理的に災害に関与した人(または人々)。となっている。
先ほどの例に当てはめると、五次被災者は"テレビ中継などで火災現場を見て不快な感情を持った人"、六次被災者は"火災の原因が外部にあり、その原因を作った人"であると言える。
以上のことから、被災者と外部との境界線を見つけることが難しいことが分かる。また、救援者やボランティアも被災者になることがあり、一概に被災者を、“災害の中心にいた人”と言うことはできない。”
Wikipedia「被災者」より引用
ちょっと引用多すぎて長くなったので、ここまでを前編ということにして次回に続きます(笑)。
今回は3月17日に川棚町の土花墓地にて解体工事をやらせていただいた際に、いつも仕事のお手伝いをお願いしています「ふるた墓石店」社長の古田さんと、一度くらい解体の経験してみるか?というコトで助っ人(?)参戦してもらった僕の愚息三人とで、古田さんの息子さんオススメのラーメン屋さん「えぞっこラーメン 展望台」さんにて昼食をいただいた写真をアップしておきましょうか。おそらく店名の“えぞっこ”が意味するところとして札幌ラーメンのお店と推測するので、主役は味噌ラーメンなのだろうとは思うのですが、ここは敢えて古田さんの息子さんオススメの醤油ラーメンに、半チャーハンと半餃子セットを注文してみました。
いやぁ、長崎では珍しいと思われるプリプリのちぢれ麺で、ちょっと濃い目のスープがよく合って愚息と共に大満足。とても美味しいラーメンでした。ごちそうさまでした、また寄せていただきます。なんかグダグダですみませんw

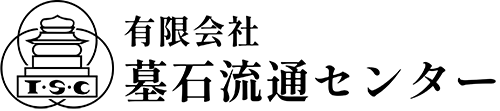
 お問い合わせ
お問い合わせ
