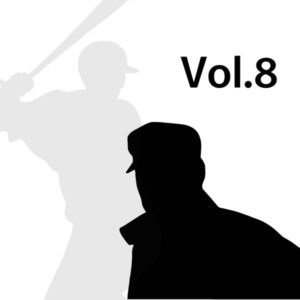Vol.9: 早速万博行ってみた(中編)
確か前々回のお話の際に、4月26日に万博に行ってうんたらかんたらお喋りしていたと、ほんのり記憶がありますので、もうあれからかれこれ2か月以上が過ぎようとしているんですねぇ…
全然“早速”ではなくなりましたが、そんなことはサラリと無視して元気よく進めて参りましょう。
間にどうしても語らずにはいられない出来事が起こっちゃいましたので、一話挟んで中編となりますが、前編ではどこまでお喋りしたっけな…ちょっと読み返してみますと、そうそうゲートくぐって、こりゃ広いなぁと思ったのと僕ら全く準備出来ていなかったので、人気のある、つまり観るべきパビリオンは観れないことを悟ったところまででしたか。
後編行く前に僕が最初にExpo2025をお題に取り上げた際に、ChatGPTさんに教えてもらった、大阪万博のテーマ・サブテーマ、それに特徴と見どころを再度記載しておきましょう。
テーマ:「いのち輝く未来社会のデザイン(Designing Future Society for Our Lives)」
サブテーマ:
- Saving Lives(命を救う)
- Empowering Lives(命に力を与える)
- Connecting Lives(命をつなぐ)
特徴と見どころ:
- 未来の技術の展示:AI、バイオテクノロジー、宇宙開発、脱炭素技術など。
- 各国のパビリオン:世界中の国や国際機関が出展し、それぞれの文化や未来ビジョンを紹介。
- スマートシティの実験場:会場自体がIoT・モビリティ・脱炭素の実証実験の場となる。
- バーチャル万博:リアルに行けなくても、オンラインでパビリオンやイベントに参加可能。
※「日本国際博覧会」ChatGPT より引用
これね、テーマとかサブテーマは確かに予約の必要なく並んで観ることが出来た「大阪館」という、夢洲駅側だから東口だったよな確か、東口ゲートを入って大屋根リングまでの間、正座して「いらっしゃいませ!」しているミャクミャクをちょっと過ぎた右側にある、屋根から水が流れて涼し気なパビリオンにて、なるほど…なんとなく言わんとすることは解るような気がするとは思いました。

命が輝くとかいう言い回しは僕にはよくワカランのですが、未来の社会をイメージするに充分な、循環を大切にしたインフラシステムのあれこれを拝見することが出来ました。
特に僕が興味をひかれたのは、未来の下水処理システムですかね。iPS細胞の第一人者として名高い山中伸弥教授の研究内容ですとか、1970年の大阪万博で発表され未だに実用化されていない“人間洗濯機”の現代版として展示及び実演されていた“ミライ人間洗濯機”なる発明品ですか、ああいった目を引く展示品に関しては、万博会場に行かずともすでにネットなどで知識としては持ち合わせていたりするので、下水処理システムみたいな地味だけど生活から切り離せないインフラの未来とかを知れるのはとても良いと感じました。
そうは言っても、例えば動画などで山中教授のお話を聞けたり、人間洗濯機なるもののシステムとその実用性などを知識として得ることは出来ても、やはり実物を見たり触れたり、あるいは実演しているその瞬間を実際に見るという機会が得れるのは、万博にしかない良さなんだろうとも実感しましたね。
まあ、いずれ来るかもしれない未来を、来てもいない今知る必要があるか?とか、来てから知ればいいんじゃね?とか、
そういうロマンの欠片もないご意見には耳を傾けませんのであしからず(笑)。
大阪館を出て、いよいよ大屋根リングに向かった僕ら。
親友Tとその息子くんはあまり興味をそそられていなかったみたいですが、僕は日常的に「水平」やら「直角」やらを気にせざるを得ない職業についていることもあってか、大屋根リングの構造に興味深々で、内部に入って内側か使用されている木材の一つ一つを見て、これは凄いなぁと、正に開いた口が塞がらないとはこのこと、うわぁ…と口が開いたまま周囲を見渡してしまいましたよ。
勿論、部材の一つ一つは直線で出来ていて、その組み合わせで円を作っているのであろうことは想像出来ていましたが、実際に見るとこの巨大な建造物をよく作ったなぁと、感動を通り越して半ば呆れに近い気持ちで、水平をとるため接合部に挿してある金属製の“くさび”を眺め、気の長くなるような作業工程を想像して楽しんで来ましたよ(笑)。

ぶっちゃけ言いますと、これを「木造建築物」として作ろうと考えるのは世界中探しても日本人だけじゃないかな?
おそらく、世界にこの大屋根リングを作るための建築技術を持つ国は想像しただけでも数か国はあると思いますが、実際に木でこれを作ろうと考えつくのが日本だけだと思いますよ。正直言ってこれほどの規模の木造建築物を、現代においては作る必要性がありませんから(笑)。
しかも万博終わったら解体撤去ですからね…
とりあえずCopilotさんに「大屋根リングの設計者は?」と聞いてみましたので、回答を以下に記載しておきます。
大屋根リングの設計者は?
大阪・関西万博の「大屋根リング」の設計者は、世界的に活躍する建築家の**藤本壮介(ふじもと そうすけ)**氏です。🌟藤本壮介氏について
- 日本を代表する現代建築家の一人で、自然との共生や未来的な都市像をテーマにした作品で知られています。
- 「大屋根リング」は、2025年の大阪・関西万博のシンボル的存在であり、世界最大級の木造建築としても注目されています。
- リングの設計には、日本の伝統的な木造技術と現代の構造工学が融合されており、円形の構造が「調和」や「循環」を象徴しています。
ついでに「大屋根リングの施工業者は?」も聞いてみました。
大屋根リングの施工業者は?
大阪・関西万博の「大屋根リング」の施工は、複数の大手建設会社が工区ごとに分担して行っています。
主な施工業者は以下の通りです:■工区【西工区】
主な施工業者|竹中工務店 |
特徴| 木造建築の施工において、ジャスト・イン・タイム方式やデジタルファブリケーションを導入し、効率的な施工を実現。
■工区【北東工区】
主な施工業者| 北東工区 | 大林組・大鉄工業・TSUCHIYA 共同企業体
特徴| 木材の接合に伝統的な貫工法を改良し、再利用可能な構造を目指した施工を実施。国産材(四国産ヒノキ、福島産スギ)を積極的に活用。補足情報:
- 照明設備はパナソニック エレクトリックワークスが担当し、クラウド制御による幻想的な演出が話題になっています。
- 各工区では、木造建築の伝統技術と最新技術の融合がテーマとなっており、施工そのものが未来の建設業への挑戦とされています。
ここに日本人以外の作業従事者が一人も入っていないことはないかもしれませんが、設計・施工いずれも日本の技術者の皆さん方が力を挙げて作られ、
木材も国産のヒノキやスギを積極的に活用とありますので、大屋根リングという建築物そのものが、
現在の日本の建築に携わる人々の想いや誇りを形にしたものということなのかな。
ちょっと大袈裟かもしれんですが、まあこれは解体される前に一度観ることをお勧めしますよ。
一周およそ2㎞だったと記憶しますが、大屋根リングの上を歩いてみると眺めがまた良くてね。


まあ、単純な僕らはおよそ半周しようかというところで見えてくる“アレ”に目を惹かれ、スタート時は「よ~し!2㎞歩いてみようぜ!」とか言ってたのも忘れ、“アレ”に吸い寄せられるように半周した西口側で大屋根リングを降りちゃうことになるワケですが。


大屋根リングについつい熱くなっちゃいました。
今回を中編にして、残りを後編としてアップします。あんまり長いとT辺さんに怒られちゃうんで(笑)。
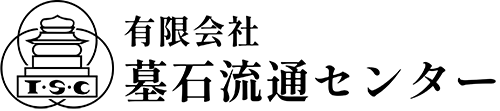
 お問い合わせ
お問い合わせ